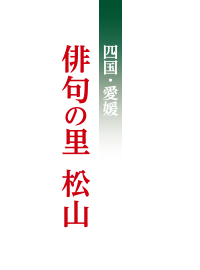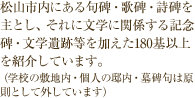道後コース(7)
伊豫の湯の汀にたてる霊の石
これそ神代のしるし成ける古歌
松山市道後湯之町の道後温泉本館北側に丸い大きな石が木の柵に囲まれて安置してあり、その手前に右の和歌が円柱に刻まれている。
この歌が古書に見えるのは、天和2年(一六八二)に、全国にその名を知られた岡西惟中という俳諧の指導者が、亡妻追善の気持ちを込めて当地を巡歴した記録である。
その記録を『白水郎子記行』(あまのこのすさび)と言い、序文は天和3年(一六八三)となっているから、三百年以上も前のことになる。それによれば、大穴持命と少彦名命の二柱の神がこの国をめぐり給う時、大穴持命の治め方が手荒いのを恥じて絶え入ったのを少彦名命が驚いて温泉に浸したところがこの石の上で玉石を「ふみまろばして起きあがりき。その玉の石四尺まはりのたゞうつくしく圓なるかたちしててりかゝやきぬ。いまに湯の前にみえ侍り。古き哥に」と前書きして、この歌がある。明治早々の本県地誌の『愛媛面影』にも、この玉の石の姿が木版に刻してあるが、その姿は今日の姿と全く違わない。このあたりの姿が、「道後のシンボル」とでも言えようか。

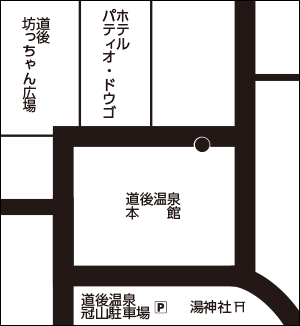
所在:松山市道後湯之町(道後温泉本館北)
道後コース(7)番